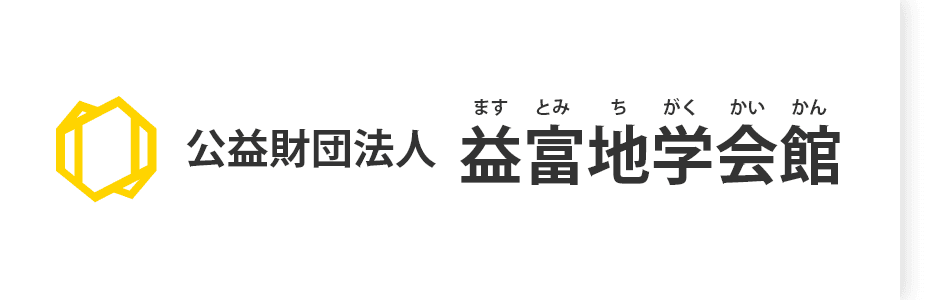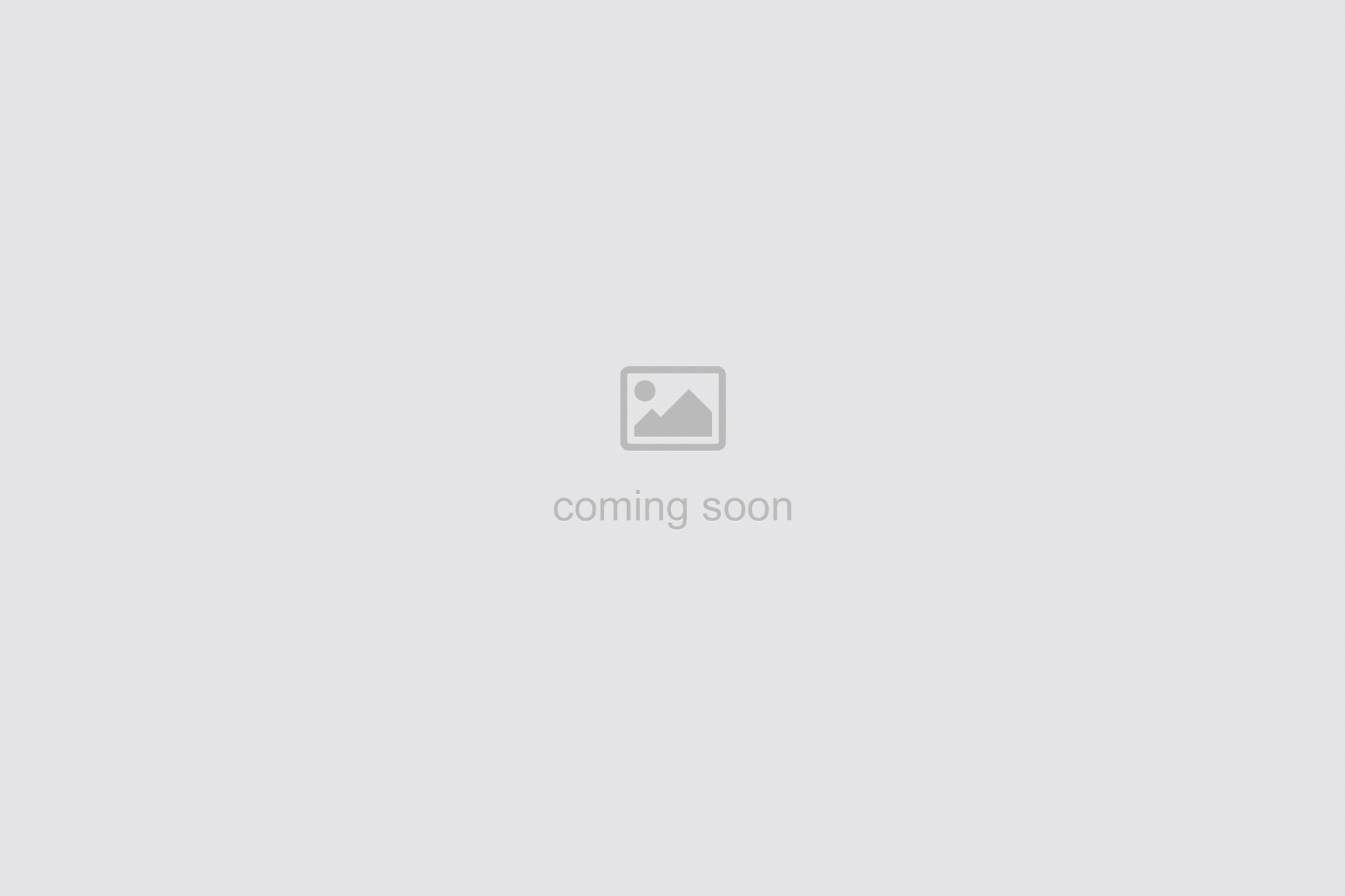2024年7月19日
『岩石薄片教室』のご報告
2024年7月13日(土)に『偏光顕微鏡の見方教室』,14日(日)・15日(月・祝)に『薄片作製教室』を実施しました.
7月13日 偏光顕微鏡の見方教室
『偏光顕微鏡の見方教室』では,まずは身の回りにはどのような岩石があるのかを紹介した後に,偏光とは何か・偏光で見ることでどのような観察ができるのか、簡単に説明がありました.その後,花崗岩に含まれる石英・長石・雲母や玄武岩に含まれるカンラン石・輝石・斜長石など,代表的な造岩鉱物を実際に観察する中で,偏光顕微鏡の扱い方を学んでいただきました.
偏光板を入れた時の薄片の見え方やステージを回転させるごとに消えたり現れたりする様子は,初めて観察する方にとっては新鮮であったと思います.偏光板の出し入れを繰り返して,偏光板を入れた時・抜いた時の両方の特徴を意識しながら観察するのは難しかったようですが,それでもみんな少しづつ偏光顕微鏡観察に慣れていきました.
7月14、15日 薄片作成教室
『薄片作製教室』では,まずは薄片作成の手順についての説明がありました.いい薄片を作成するためには薄片の厚さを均等にしなければいけませんが,そのためにはまずはスライドガラスに張り付ける岩石チップが平らになっている必要があります.これが薄片作成の中で最も肝心なのですが,幸い今回の教室ではあらかじめ指導者の一人である北川さんがやってくださっており,受講者はスライドガラスに岩石チップを張り付けた段階から始めることができます.
手順の説明の後,それぞれ3枚好きな岩石を選択して薄片作成開始.まずはダイヤモンドカッターで0.5~1㎜程度に二次切断し,そこから鉄板で320番の研磨剤を使って粗削りしていきました.岩石により難度は異なりますが,みんな慎重に一枚目のチップを適度な薄さを目指して粗削りしていきました.二枚目・三枚目のチップになると慣れてきたのこともあり比較的早く粗削りを終える方もいましたが,中には岩石ごとの硬さを読み違えて岩石チップを一部削り飛ばしてしまう方もいました.
岩石薄片の偏光顕微鏡観察は,岩石種や岩石に含まれる鉱物種を決定するにあたりとても重要な観察方法です.今回の参加された方はこれをきっかけにして,自身でも岩石薄片作成にチャレンジしてみてはいかがでしょう.会員の方であれば,益冨地学会館でも作成することが可能です.